当院が考える矯正治療とは
当院は、遠方(国内外)の患者さんが多く、一般の矯正治療はもとより、より専門性の高い保険適用の口蓋裂・顎変形症などの難症例や、セカンドオピニオンの相談、転医希望など様々な理由でご来院いただいています。
当院の基本とする5つの柱
長年、矯正治療の臨床・研究・教育に携わってきた経験から、矯正治療に対する当院の基本は以下の5つと考えています。
5つの要素の統合による矯正治療
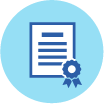
1.治療技術

2.患者さんの不安を共有する姿勢

3.臨床教育経験

4.歯科衛生士の口腔ケア

5.継続的な研究姿勢
1.治療技術
スタンダードエッジワイズ法による矯正装置
当院では、矯正治療学の歴史において最も長く矯正医が使用し、また、現在の各種テクニックの基本ともなっている「スタンダードエッジワイズ」を主要装置として用いています。
「スタンダードエッジワイズ法」とは、矯正装置(ブラケット)に通すワイヤーを、それぞれの患者さんに合わせて医師が個別に屈曲して歯を移動させるテクニックです。技術と経験が必要な方式ですが、緻密で綺麗な歯並びに仕上げることができます。
目立たない装置をご希望の方には
装置の組み合わせや治療法により、解決に努めています。
目立つことが気になる方は、透明の装置や歯の裏側の舌側矯正装置もお選びいただけます。
また、金属アレルギーなどについても精査した上で装置の選択を行うようにしています。
一人の担当医による総合的な治療計画
歯を効率よく移動させることについては「〇〇システムの使用」というよりも、まず一人の担当医が継続的に治療にあたることが基本となります。担当医が毎回代わる状況や矯正治療に慣れていない歯科衛生士が入れ代わり対応することは望ましいとはいえません。
加えて、患者さんの成長発育の評価、協力度、不安因子の軽減、生体の反応系、日常生活におけるストレス度、栄養、口腔ケアの充実、ワイヤーの種類・デザインなどを考慮した総合的な治療計画により、スムーズな治療が行われると考えており、これらは矯正医として当たり前のことと思っています。
2.患者さんの不安を共有する姿勢
患者さんの不安はさまざま
患者さんはどなたも不安いっぱいです。初診時、治療中、治療を終えてからもあります。
「この先生で本当に大丈夫?」「痛くない?」「治療費は?」「後戻りしない?」「試験の時は?」「仕事上の不都合は?」「結婚・出産の時は?」「留学の時は?」「転居・転勤の時は?」「スポーツや楽器の演奏時は?」「かっこ悪くない?」「歯磨きは?」「虫歯は?」「発音は?」「食事は?」…。
数え上げればきりがありません。
でも、これは当然なことです。
このような日常的な心配や不安がある中で矯正治療は進みますので、できるだけ患者さんの抱える不安要素を共有しようと思わない限り、治療はスムーズに進みません。
その意味においても、患者さんの不安を共有する姿勢は必要不可欠なものです。意識の共有は、受付、歯科衛生士、担当医ともに重要な仕事と考えます。
患者さんの立場に立って、正しい説明を
患者さんには耳障りの良いことだけをお話しするのではなく、当たり前のことを当たり前に説明するよう努めています。
「早く治る」「ワイヤーを使わない」「抜歯しない」などのトピックス的な矯正情報がありますが、そういったご要望をいただいた場合も、それらの処置が治療上論理的に説明できない場合には対応をご辞退させていただいています。
無理な治療設定や論理的矛盾を持っての処置は不安に繋がり、患者さんにとって得策でないと考えるからです。
3.臨床・教育経験
矯正治療を行って48年目(令和5年時点)となりました。担当した症例数は東京医科歯科大学、昭和大学、開業経緯を含めて、一般の矯正、口唇口蓋裂、顎変形症、特殊な先天疾患を伴う難症例など多くの治療を行い、現在に至ります。
教育・研究は、歯学部、歯科衛生士、歯科技工士に携わって30年を経験しました。治療に関しては医科歯科の専門医とのチーム医療、ならびに当院スタッフとの共同作業が特に重要であることを認識しています。
これらは私の臨床の財産です。
4.歯科衛生士の口腔ケア
矯正治療中、虫歯や歯肉炎、歯周病などの出現の心配はあります。心配や不安を軽減するため、当院では担当医の処置前に歯科衛生士が毎回約30分程度の口腔ケアを行います。
口腔ケアの時間中、患者さんの心配や不安をできるだけ多くお聞きするように努めます。口腔ケアに対するアドバイス、口腔ケアのチェック内容は、衛生士から担当医へ伝えられるようにし、常に毎回の処置をダブルチェックするように努めています。
このような治療システムを取るため、一日に診させていただく患者さんは20~30名に限定させていただいています。
5.継続的な研究姿勢
「新しい矯正治療法」への考え
トピックス的に取り上げられる「新しい矯正治療法」という情報のいくつかは、極端に素晴らしいものとは思えません。「治療期間が短い」「抜歯しない」「ワイヤーを使わない」など、誤解を招きやすい表現に関するセカンドオピニオン的な相談も少なくありません。
2008~2011年に当院でセカンドオピニオン面談調査を行いました。その結果、患者さん自身の誤解もありますが、やはり大げさな表現や担当医の説明能力不足などが、トラブルの主な要因として挙げられました。
一例ですが、「ワイヤーを用いない新しい矯正治療という方法がありますが、どうでしょう?」という相談も、論文を読まれている先生であれば、1970~1980年代に東京医科歯科大学の先生が、また改良型も昭和大学の初代の教授などにより提唱され、現在でも当たり前のように用いられているものであることを知っていると思います。
違いがあるとすれば、装置の素材、コンピュータを用いた装置制作システムというところです。もちろん装置そのものは軽度な症状の改善には効果的ですし、患者さんの過度な金属アレルギー、どうしてもワイヤーを装着したくない、などの理由でその装置を使用することはあると思います。しかし、本格的に個々の歯を3次元的に位置づけるという処置に対しては、いささか疑問が残ります。
当院の姿勢
特定の治療方式で「どのような症例でも治療が可能」と思わせる表現をすれば、セカンドオピニオンを求める患者さんも増えるのではないかと思います。
心配や不安を持たれる患者さんに対しては、適切な説明が必要となります。そのためには、論文抄読やクリニック自身の継続的な調査研究姿勢が大切だと考えています。